海外在住者として
ドイツに生活拠点を移してから、もう10年目となった。その間にいわゆる永住権は取得できたが、国籍をドイツに変えることは考えていないので、当然ながら今でも外国人としてここで暮らしている。
私が日常生活の中で折に触れて考えることの一つが、「マイノリティであるとは何か」ということ。移民大国のドイツとはいえ、もちろんドイツ人が多数派で、外国人は少数派。ヨーロッパ圏外の外国人、つまり日本人の私などは、その中でも更にマイノリティだ。
マイノリティといえば、個人レベルでいじめや、社会レベルで迫害の対象になりやすいというイメージがある。一方で、「個性的」「特別」とポジティブに捉えることもできるのではないか。この記事では、マイノリティとして生活する海外在住者の私が日々考えていることを、気の向くままに記してみたい。
迎合できない性格
おそらく最初に記しておかないといけないのは、そもそも私が、多数派に属さないことはむしろ好ましいと、子どもの頃から感じていたことだ。小学校時代から、クラスの中でグループを形成する(特に女子の)文化に馴染めず、一匹狼のように過ごし、「周りと違うことをしたい」「普通ではいたくない」という気持ちがずっとあった。
物心が付いた頃には「個性的であること」を重視していた気がする。誰かに迷惑を掛けたり、非難されたりしない範囲で、いつも個性的なファッションをしてみたり、子ども向きとは言えない外国の文学作品を読み漁ったりし、やがてイギリスとドイツに留学して、「自分が外国人になる」という鮮烈な経験をした。そして最終的にドイツに拠点を移し、ここで外国人として生きていくことを選んだ。
周りの調和を乱したいわけではないけれど、風潮に迎合するのは無理、そして多数派の一員として埋もれてしまうのは嫌、という私の元来の性質を前提としたうえで、これから考察を進めてみる。
外国人の自分
外国人であるというのは、マイノリティとして一番わかりやすい例だろう。良くも悪くも、周りとは違うので目立つ存在になる。
例えば、私が通っているバレエのオープンクラスにほぼ毎回来ているコアメンバー約10人は、半数はドイツ人、あとはヨーロッパ人やロシア人など国際色豊かだが、日本人は私だけである。

私は目立ってバレエが上手なわけでも会話が得意なわけでもないが、「日本人」という強力でわかりやすい特徴があるので、それだけで何となく個性的なキャラクターとして成立してしまう感じがある。
そして、外国でマイノリティとして暮らしていると、それと意識しなくても、草の根親善大使のような役割を担ってしまう。私の知り合いや友人にとっては、私が唯一の身近な日本人であることも多いので、「日本=Aki」とイメージが直結している可能性を忘れてはいけないな、とよく自戒する。つまり、日本や日本人のイメージをむやみに悪くするようなことはしないよう気を付けたいと思う。
もちろんこれは、どの国の出身者にも言えることである。例えば私の隣人にはちょっとシャイなスコットランド人男性と明るいドイツ人女性の夫婦がいるが、私はその男性しかスコットランド人の友人がいないので、「スコットランド」と聞くと自動的にその人を思い浮かべてしまう。
日本については、ヨーロッパで持たれているイメージは概して良いので、イメージアップに躍起になる必要性は感じていない(先人に感謝しなければならないと心から思う)。一方で、ロシア人やアメリカ人など、現在世界的に「問題がある」と認識されている国が出身のマイノリティは、偏見を持たれることもあるに違いないので、勝手ながら気の毒だ。
女性としての苦悩
ドイツで自己紹介文を書くことがあれば、私はまず「日本人女性」と書く。つまり日本人であることと並んで、女性であることは、自分の特徴の主軸となっている。
人口統計的に考えれば、もちろん女性であることはマイノリティではない。ドイツ連邦統計局のデータを見ると、むしろ女性の割合の方が男性よりも若干高くなっているほどである。
一方で、職場にいると女性はマイノリティという感じがするので不思議だ。この点ではドイツよりも、やはり日本の方が“遅れている”と感じる。
私が勤めているのはドイツにある日本の機関だが、特にマネジメント層はいまだにほぼ男性のみ。これは最近変わってきてはいるが、やはり出世した女性がいると、「女性なのに」すごい、という前置きが付きがちである。女性が社会的にハンディキャップを負ってきた長い歴史を考えると、すぐにはどうしようもないことだとも思う。教育の機会や参政権が平等に与えられて久しい現代でも、「女性なのに」という感覚が完全になくなるまでには、あと数十年必要かもしれない。
私はジェンダーという観点では、LGBTQ+といったセクシュアル・マイノリティには該当せず、男性と結婚しているので、いわば多数派である。一方で、私たちはいわゆるDINKs(Double Income No Kids、共働きで子どもを持たない夫婦)だが、これはやはり少数派のライフスタイルで、特に日本では理解を得にくい。元々マイノリティに属することに抵抗のない私ですら、この点ではかなり圧を感じている。
不平等なことに、「子どものいない男性」よりも「子どものいない女性」に対する偏見や批判は根強い。何か少しトゲを感じるコメントをされるたびに、「少子化に加担するなんて、社会に対する責任を放棄している」「好きなようにお金と時間を使って生きたいなんて自己中心的」「孫ができない親がかわいそう」と、糾弾されている気分になってしまう。「結婚する」「子どもを持つ」ことが幸せの前提とされ、むしろ義務に近かった社会から、各自が自分の幸せのあり方を周囲からのプレッシャーなしに選べる社会に変容するまでには、まだ時間が必要そうだ。
「マイノリティはクール」なベルリン
ジェンダーといえば、最近とてもベルリンらしいと思う舞台を観た。ベルリン国立バレエの新作で、シェイクスピアの喜劇を基にした『Ein Sommernachtstraum(夏の夜の夢)』。
主役と言っていい悪戯好きな妖精・パック役に抜擢されたのが、ノンバイナリー(性自認が男性・女性に当てはまらないと感じている人)の南アフリカ共和国出身のダンサーだったのである。

後でインタビュー記事を読んだところ、男性として生まれたがずっと違和感があって、バレエでは男性役と並んで徐々に女性役も踊るようになり、現在は女性側にいる方がしっくりくるので代名詞は「she(ドイツ語:sie)」を使っているという。
男性でも女性でもないダンサーが踊るパックは、まさしくはまり役だった。第一幕はバレエシューズ、第二幕はトゥシューズ(伝統的には女性しか履かない)での振付だったが、小柄で筋肉質な身体に繊細さも兼ね備えた表現で、妖精という異世界の存在にぴったり。カーテンコールでも特に拍手喝采だった。
更には南アフリカ出身ということで、二重にマイノリティと言ってよいだろう。バレエの世界は今でこそアジア人など白人以外も少なくないが、やはりヨーロッパ人が多数派である。
オープンさを売りにしているベルリンでは、ダイバーシティを前面に押し出すことが社会的にも政治的にも評価され、マイノリティ=特別=クールとポジティブに捉えられる傾向がある。時代や地域によっては差別されただろうダンサーの特性を逆手に取った、話題性のある巧みなキャスティングだった。
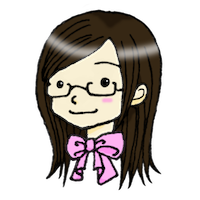
個人的には、やがて「多数派」「少数派」という区分の意識もなくなって、みんな違って当然、みんな違ってみんないい、という世界になるといいなと思っています
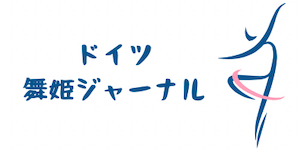


コメント
いつもドイツ舞姫ブログを拝見しています。
バレエのことはほとんど知らないので、貴ブログの記事で学んでいます。
ご存知のように、日本は女性の地位が低いです。女性の政治家や経営者もまだまだ少ないために、閉そく状態から脱していけてない様な気がしています。
また、経済的理由などで、未婚者・非婚者が増え、子を持たない夫婦、持ちたくても持てない夫婦、授かり難い夫婦も増えている様子で、少子化を不安視する向きが多いです。そこは不本意かも知れませんが、多様になることは悪くないと言う観方もあっても善いのではと思っています。
少し外れるのですが、日本人と言うかアジア人差別的なところは、ドイツでは如何でしょうか。米国では今でもある様子ですが。
最後にあった”みんな違ってみんないい”が広まってほしいですね。(もしかすると、金子みすゞでしょうか)
ではまたいつか。
いつもコメントありがとうございます。
日本における「女性の本来の居場所は職場ではなく家庭」「子どもを産んでこそ女性」という固定観念は、60〜70代の私の両親の世代ではまだ顕著ですが、私の世代ではだいぶ薄れてきていると感じます。
母性神話というものは、資本主義経済の発展に合わせて大正時代に人工的に作られたものなのだそうです(男女問わず家や近隣で働く形態から、男性は企業に出勤して日中は家にまったくいないという形態に変わっていったため、仕事と家事・育児の分業が進み、後者は女性が一手に引き受ける必要が出てきた)。
在宅勤務も一般的になってきていますし、これから急速に変わっていくかもしれませんね。
おっしゃる通り、生き方が多様化して、結婚するかどうかも子どもを持つかどうかも、義務感や劣等感なくそれぞれ選択できる社会になってほしいです。
アジア人差別はドイツでもあるにはありますが、私が今まで住んだことのある都市ではアジア系移民がとても多く(例えばベルリンには大きなベトナム人コミュニティがあります)、アジア人であっても目立たないためか、あまり感じることはありません。
私が明らかに「アジア人だから馬鹿にされたな」と感じる出来事は、一年に数回あるかどうかです。
確かに、「みんなちがって、みんないい」は金子みすゞの一節でしたね!学校の教科書で読んだはずで、記憶の奥底に眠っていたのが急に顔を出したみたいです。