ドイツ語から文化考察
おそらくこのブログを読んでくれているのは、ドイツに関心や繋がりのある人がほとんどだと思うので、ドイツ語に触れたことがある人も多いのではないだろうか。ドイツ語圏在住という人も、現在進行形で勉強中という人も、「そういえばずっと前に大学の第二外国語として習ったなぁ」という人もいるだろう。
この記事では久しぶりにドイツ語をテーマとして、そこから見えてくるメンタリティの違いや、ドイツ国内での地域差について考察してみたい。
「きみ」と「あなた」の違い
「二人称」、つまり英語でいう「you」にあたる言葉が、ドイツ語では二種類あり、親称の「du(複数形はihr)」、敬称の「Sie(複数形もSie)」と呼ばれる。日本語では「きみ(たち)」「あなた(たち)」と訳されることが多い。
二人称に親称と敬称の区別があるのは、例えばフランス語の「tu」と「vous」のように、ヨーロッパの多くの言語で見られるので、馴染みがある人も多いかもしれない。
この区別について、私の母校のオンライン言語モジュールにわかりやすい説明があったので引用すると、
家族、親戚、友達などに対しては親称の du/ihr を使います。若者同士や学生同士などは初対面でも du/ihr で話します。敬称のSie は特に親しくない相手、言いかえれば、社会的に一定の距離を置く相手に対する言い方です。最初は Sie で話していても、親しみを感じて「du にしようよ」と片方が持ちかけたら、それから後はお互いに du で話すようになります。また、親称と敬称の使い分けは原則として相互的です。つまり、親が子に対して du と言えば、子も親に対して du と言います。
duで話す相手とはファーストネームで呼び合い、Sieで話す相手とは苗字で呼び合うのが基本だ。
主語としての二人称が変われば動詞の活用も変わる。無理やり日本語に例えると、「タメ口」か「敬語」かの違いに近い。
日本語では英語の「you」にあたる言葉が、二つどころか色々とある。まず「あなた」「きみ」「おまえ」などが思い浮かぶが、実際の会話ではあまり用いることはなく、相手のことを言っていると文脈で明らかな場合には省略したり、「〇〇さんは…」「〇〇くんは…」と名前で呼んだりする方が普通なので、あまり意識することはないかもしれない。これについては以前、名前を呼ぶ意味 - 日独比較という記事でも考察した。
duかSieか問題
さて、このduで話すかSieで話すか、というのは意外と難題で、ドイツ人でも迷うという。例えば職場では両方が混在している。
外部の取引先や顧客とはSie、というのはわかりやすい。社内であっても立場上大きな距離があれば(例えば社長と一般社員)、Sie。ここからだんだん曖昧になってきて、上司と部下はSieが基本だが、オープンな雰囲気の職場であればduもあり得る。あまり立場の変わらない同僚同士はduが普通だが、歳が大きく離れているとSieということもある。

あまり話す機会のない職場の人と久しぶりに顔を合わせると、「あれ、私この人とduで話してたっけ、Sieで話してたっけ」と記憶を探ることがあります
duからSieになることは基本的にないが、Sieからduに切り替わることはよくある。基本的には目上・年上の人から「duにしない?」と提案する。
例えば最近、私の職場に20代のドイツ人職員が新しく入ってきた。大学院を出て初めての就職ということで、初日は緊張した面持ちで、ひとまずSieで話しながら周りとの距離感を掴もうとしていたが、私も含め同僚たちは自己紹介しつつ「duでいいよ」と最初に伝えた。
親しき中にも礼儀あり、ということで、Sieを使うべきシーンではきちんと使うことも大事。私のドイツ人の夫・ベルリーナーDは先日体調を崩し、かかりつけの医師に電話で症状を説明していたのだが、「最後になってうっかり先生をduで呼んでしまった、あぁ恥ずかしい」と後で落ち込んでいた。まだ30代くらいの若い先生だが、医師と患者という関係性では、当然ながらSieで通すべきところである。
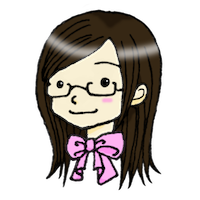
私はむしろ、ドイツ人でもこういう間違いをするんだな、と励まされましたが 笑
ベルリン特有の現象
私は中世の名残を感じるドイツ南西部のハイデルベルクで何年間か大学に通った後に、北東部の首都ベルリンに引っ越してきた。

ドイツ国内とはいえ雰囲気も文化もまったく違うので軽いカルチャーショックを受けたが(京都から東京に引っ越した場合を想像してもらうといいかもしれない)、その一つが「duとSieの使い分け」だった。
重厚な歴史を感じるハイデルベルクでは、例えこちらが見るからに若い学生であっても、接客を受ける場面では「Sie」で話し掛けられた。ところがベルリンに来てみると、カフェでも、アパレルショップでも、ちょっとお洒落なレストランでも、「du」!
知らない店員からduで話されるということに最初は大きな違和感があったが、しばらくすると慣れてしまった。この点について生まれも育ちもベルリンのDに聞いたところ、
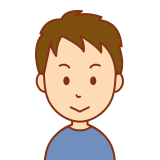
店員からSieで話されると、「ぼくももうそんなに歳に見えるのかな」ってちょっと悲しくなるよね…
とのことで、やはりduで話される方がしっくりくるらしい。
ベルリンでは若い人同士だけがduで話すかというと、そうでもない。私は緩く社交ダンスを習っていて(社交ダンス歴数十年の同僚が職場の昼休みに希望者に教えてくれている)、先日初めて社交ダンススタジオのイベントに仲間と参加した。

私たちは30~50代、スタジオの生徒と思われる他の参加者たちは60~70代が多かったが、初対面でも「du」で声を掛けられ、一緒にワルツを踊ることになった。
私が長く通っているバレエスタジオもオープンな雰囲気なので、どんなに年齢差があっても、先生と生徒は最初からduで話す。一方で、スタジオの入り口で受付のアルバイトをしているのはティーンエージャーのことがあるが、先日その若者から「Sie」で話し掛けられて、「確かに母親と同じくらいの世代かもしれないし、さすがにduでは話せないよね…」と思いつつ、Dの言っている悲しさが少しわかる気がしたのだった。
他言語と比べて
duはタメ口に近く、Sieは敬語に近い、と上述したが、ですます調はその中間くらいに位置しているイメージ。つまり、ですます調を使う相手とは、ドイツ語ではduにもSieにもなりうる。例えば親しい同僚であっても、よほど歳が近くなければ、(ドイツ語ではduでも)日本語ではタメ口ではなくですます調になるだろう。
他の言語では、敬称(Sie)から親称(du)に移るまでの壁はドイツ語より高いことがあるようだ。私がハイデルベルク大学でフランス語を教わっていた独仏ミックスの先生は、
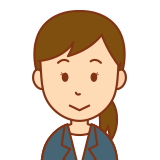
フランス人の夫の両親とは私も仲がいいですが、フランス語ではやはり敬称のvous(ドイツ語でいうSie)で話します。ドイツ語だったらduになっていると思いますが
とのことだった。日本語でもやはり、義理の両親とはタメ口ではなく、丁寧に話すところだろう。そう考えると、親しくなれば割とすぐに親称のduに切り替わるドイツ語は、言語的・心理的な距離を縮めやすいという特徴があるのかもしれない。
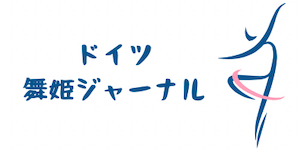


コメント