西洋から見た東洋
「バレエ」と聞くと、「西洋が舞台」と思うのが普通だろう。イタリア・フランス・ロシアを軸に発展してきた舞台芸術だが、実は多くの東洋趣味が取り入れられている。わかりやすい例だと、『くるみ割り人形』の「中国の踊り」や「アラビアの踊り」が思い浮かぶ。
異国情緒に惹かれるのは、どの時代でも、どの国でも同じ。ヨーロッパのお城や宮殿に行くと、よく中国や日本の陶器を集めた豪華絢爛な小部屋があるが、日本人が西洋に憧れてきたように、ヨーロッパ人も東洋に憧れてきたのである。

バレエ好きなら、一度は観たことや発表会で踊ったことがあるだろう『ラ・バヤデール』は、古代インドが舞台。1877年にロシアのサンクトペテルブルクで初演された。振り付けはマリウス・プティパ、チャイコフスキー三大バレエの考案者として知られる伝説的振付家である。
今シーズン、ベルリン国立バレエの公演を2回観にいったので、この異国情緒溢れるバレエ作品の面白さについて考えてみたい。
あらすじ
バレエ団によって色々なバージョンがあるが、ベルリン国立バレエの『ラ・バヤデール』は、初演に倣って4幕7場で構成されており、2幕と3幕の間に休憩が挟まれる。休憩を含めて公演時間は約3時間、なかなか見応えがある。
第1幕
古代インド。戦士ソロルは、寺院の舞姫(バヤデール)であるニキヤと密かに愛し合っている。大僧正もまたニキヤに対する愛を伝えるが、きっぱりと拒まれる。日が暮れてから、寺院の外で隠れて逢ったソロルとニキヤは、神に対して永遠の愛を誓う。それを陰から見ていた大僧正は、嫉妬に駆られ、ソロルへの復讐を誓う。
第2幕
ラジャは、自分に仕えている若きソロルを気に入り、娘ガムザッティと結婚させようとする。ふたりは引き合わされ、ガムザッティもまたソロルを愛する。ソロルは結婚を断ろうとするが、美しいガムザッティに惹かれ、またラジャに逆らうことができない。後から大僧正が現れ、ラジャにソロルとニキヤの関係を告げ口する。
この話を聞いていたガムザッティはニキヤを自室に呼び寄せ、ソロルは自分と結婚するのだから別れるようにとあの手この手で迫るが、ニキヤはショックを受けながらも頑として承諾しない。憤ったふたりが揉み合いになる中、ニキヤは思わず短剣を握りガムザッティを殺そうとするが、侍女に阻まれて逃げ出す。ガムザッティはニキヤを殺すよう命じる。
後日、黄金の神を讃える祭典で、舞姫として招かれたニキヤは悲しげに踊る。途中、ソロルから贈られたという花籠を喜んで受け取るが、そこには毒蛇が仕込まれていた。毒蛇に咬まれて倒れたニキヤに、うろたえた大僧正が駆け寄り、解毒剤を飲まそうとする。しかし、もはやソロルと結ばれないことを悟っていたニキヤは、解毒剤を拒んで息絶える。
第3幕
ニキヤを失った悲しみに暮れるソロルのところに、結婚式を思い出させようとガムザッティがやってくる。その気になれないソロルだが、ついにガムザッティの手を取ると、部屋の中にニキヤの幻影を見る。ひとりにしてほしいと頼んだソロルは、アヘンを吸い、幻覚の中でバヤデールたちの『影の王国』でニキヤを見い出して、彼女と結ばれる。
ソロルは目を覚まし、ラジャの従者に結婚式へ案内される。
第4幕
寺院でソロルとガムザッティの結婚式が執り行われるが、ソロルの視界にはニキヤの影が現れ、かつての愛の誓いを思い出させる。大僧正が、夫婦となるふたりの手を重ねようとすると、誓いを破ったことに神が怒り、寺院が崩壊して全員死ぬ。
バレエとしての特徴
ストーリーテリングの観点から言うと、『ラ・バヤデール』は古典バレエらしく、踊りとマイム(ジェスチャー)がはっきり分かれているのが特徴的である。対比するとわかりやすいのは、20世紀の代表的振付家、ジョン・クランコの作品で、純粋なダンス部分とマイムの演劇的要素が融合した『ロミオとジュリエット』だろう。
舞台が古代インドということで、エキゾティックな衣裳と舞台装飾が多い中、「これぞバレエ」と印象に残るのは、第3幕の『影の王国』のシーンである。32人の女性ダンサーが、白いチュチュとチュールを身につけて、舞台の奥から列になって一人一人出てくる。この、いわゆる「白のバレエ」(仏:Ballet blanc)は、別の記事にした『ラ・シルフィード』が原点とされている。
『影の王国』では、同じ振付(アラベスク)が32回繰り返されるのだが、前後左右にダンサーが重なり合って見えて、単純なのにこれがなんとも言えず美しい。ベルリン国立バレエの『ラ・バヤデール』の紹介ページでも、このシーンの写真がまず出てくる。
ベルリン国立バレエの公演
さて、同じ演目であっても、カンパニーによって全く違う作品に仕上がることもあるのがバレエの醍醐味。ベルリン国立バレエの『ラ・バヤデール』は、一言で言うと、「古くて新しい」。
というのも、現代の振付家、アレクセイ・ラトマンスキーが、マリウス・プティパの初演を再現しようと、研究を重ねた成果だからである。実は当時の振付の資料がほぼ完全な状態で残されているので、それを手掛かりに、プティパが何をどう表現しようとしたのか、彼の構想・意図・直感・好み・音楽との繋がりを読み取ろうと取り組んだという。舞台美術と衣裳もそれに合わせてデザインされたそうだ。
私は他のカンパニーの『ラ・バヤデール』を何度か観たり、発表会で部分的に踊ったりしたことがあるが、ベルリン国立バレエの振付は、特に第1幕と第2幕で「知っているものと違う」と思わされた。今から約150年前に考案された振付の再現は、現代のバレエを見慣れた目には、却って新鮮に映る。あらゆる回転やジャンプの技を駆使するわけではなく、比較的単純な動きの繰り返しが多かった。
具体的に言うと、例えば前アティチュード(片方の脚を軸にして立ち、もう一方は膝を約90度に曲げて体の前方に持ち上げて保つ)が多用される。『パキータ』など他の作品でもよく見られる動きではあるのだが、それがあまりに速いスピードで両脚繰り返されるので、バタバタと走っているようにしか見えないシーンも。
ドイツ人は、劇でも映画でも鑑賞中にあまり笑いを我慢しないので、思わず笑い声を漏らす観客もいた。そもそも前アティチュードでの移動は、本当に上手な人でないと、滑稽に見えかねないので、個人的にはなるべく避けたい動きの一つ。

上半身も前後させる振付のせいでもあるけれど、プロのダンサーがやってもバタバタしているようにしか見えないというのは、ちょっと問題のような気も…
その他に笑いが漏れていたのは、少々キッチュな演出のためである。ソロル率いる戦士たちが、森で獲ってきた虎を1匹、棒に逆さに吊るして担いでくるシーンや(大きな虎のぬいぐるみだと遠目にわかる)、ソロルが大きな象に乗って登場するシーンや(象の足にはローラーが付いているのだろう、従者に扮したダンサーが紐を引っ張ると滑るように移動する)、『影の王国』で踊るニキヤが手にしていた白いチュールの布が、天井から細いワイヤーでピンッ!と引っ張られて飛んでいくシーンなど。もちろん、エキゾティックさや、非現実さを強調しようとした演出であることはわかる。
また、4幕7場もあるので、場面変更が多く、一度幕が閉じてまた開くまでに、数分待つところもあったので、客席は少しざわついた。舞台からは、何かを引きずるような音も聞こえてきたので、「あぁ、今、ガラッと舞台装置を変えているところなのね」とわかってしまう。
見どころ
一方で、舞台美術と衣裳は、非常にディテールが細かく、豪華絢爛な場面でも品のある色合いが保たれ、素晴らしかった。『影の王国』の衣裳は基本的にシンプルな白いチュチュだが、頭に被せた長いチュールが両手へと流れ、ダンサーが動くたびにひらりひらりと動く様が美しい。
立体感のある舞台装置は、初演の時代からは考えられないほど進化を遂げているだろう。特に印象深いのは、一番最後の、寺院が崩れるシーン。プロジェクションを使って、建物の屋根と壁が壊れて降ってくる様が映し出される。そしてスクリーンが開くと、本当に瓦礫と化した、立体の舞台装置が再び現れる。昔なら、逃げ惑うダンサーたちの演技で、「建物が壊れていっているんだな」と伝えるしかなかったところが、現代の技術によってうまく可視化されている。

ところで、他のカンパニーの『ラ・バヤデール』であれば見どころの一つである、黄金の神(仏像)のアクロバティックな踊りが、ベルリン国立バレエ版では存在しない。踊りで特に注目されるのは、やはり主人公ニキヤと、ソロルである。
私はダニール・シムキンがソロルを踊る回と、ポリーナ・セミオノワがニキヤを踊る回をそれぞれ観にいったが、ポリーナのニキヤは本当に秀逸だった。チケットが早い段階で完売していたのも頷ける。百聞は一見に如かずと言うことで、トレイラーをどうぞ。
総じて、初演の演出と振付に忠実で、新しい技術もうまく融合させた、ベルリン国立バレエの『ラ・バヤデール』、お勧めできる。ハッピーエンドの明るいストーリーではないが、人生の不条理さもわかってくる大人になってから改めて観ると、心に響く作品である。
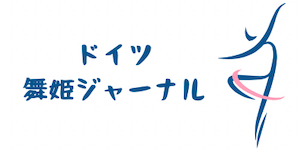


コメント