エジプトでのカルチャーショック
実際にエジプトに行ってみて初めて知ったことがある。カイロはじめ北部はアラブ系住民が多く、確かに中東らしい雰囲気を感じる。

一方で、スーダン国境近くの南部では、ヌビア人という肌の色が濃い別の民族が暮らしており、一気にアフリカらしくなるのだ。南北で別の国のように文化も言葉も違うことを、私はまったく知らなかった。
本人たちもそう言っていたが、ヌビア人は北部のエジプト人と比べても朗らかで明るく、ホスピタリティに満ちた人たち。そして、彼らとの出会いが、私たち旅の仲間4人に一番強烈な印象を残したのだった。
現在、エジプト南部で中心となっているのは、アスワンというナイル川右岸の都市。

北部カイロから中部ルクソールまでは飛行機で移動した私たちだが、ルクソールからは陸路移動を兼ねた現地ツアーに申し込んでいた。ガイドとドライバー付きの車でピックアップされ、道中にある遺跡も訪ねながら南下して、アスワンで解散というものだ。
この現地ツアーのガイドとしてやってきたのが、55歳のヌビア人・A。英語も達者な穏やかな男性で、訪ねた遺跡では壁画の意味を事細かに説明してくれ、車の中でもヌビアの文化や習慣について熱心に教えてくれた。歴史と考古学の知識が豊富で話し始めると止まらず、最終的に予定を何時間もオーバーして、ツアーの最後に組まれていたランチはディナーの時間帯になってしまったのだった。

Aもアスワン出身だといい、なんと、「君たちはアスワンのエレファンティネ島のゲストハウスに泊まるんだね。私もその島に住んでいて、ゲストハウスのオーナーとは従兄弟なんだ」というのでびっくり。

ただし後からわかったのは、ヌビア人コミュニティでは「みんな従兄弟、みんな家族」という意識だそうで、本当に従兄弟としての血縁関係があるかはあまり重要ではないみたい
この現地ツアーでは朝から晩までずっと一緒にいたので、Aと私たちはすっかり打ち解けていた。アスワンの街中ではドライバーに言ってわざわざ車を停めさせ、美味しいクッキーの詰め合わせを買ってきて私たちにプレゼントまでしてくれた。
アスワンの中心街もリゾートのようなリラックスした雰囲気で素敵だったのだが、ゲストハウスの専用ボートで迎えに来てもらい、ナイル川の中洲であるエレファンティネ島まで渡ると、ゲストハウスで出迎えてくれたヌビア人スタッフもみんな陽気で楽しい人たちだった。

私たちはこのゲストハウスに2泊して、アスワン近郊の観光地も翌々日に巡る予定だったが、それにはドライバーと車だけを手配していたので、Aにガイドを頼めないか聞いてみた。
すると、「残念ながらその日は別のガイドの仕事が入っているけど、明日の夜は予定がないから、よければ君たちを自宅の夕食に招待したい。一緒に暮らしている妹がヌビア料理を作れるから」という。
私たち4人は顔を見合わせた。知り合ったばかりの人の家にお邪魔するというのはリスクがあるし、私たちが女性だけのグループだったら、まず行かなかっただろう。でも、男性のベルリーナー・Dも一緒だったことと、ガイドの資格を持つAは教養もあって信頼できそうな人だと感じていたので、招待を受けたのだった。
翌日、私たち4人がアブ・シンベル神殿までの日帰りツアーに出掛けている間にも、Aから「気を付けて行ってらっしゃい、また夜に会えるのを楽しみにしているね」というビデオメッセージが届いた。現地ツアーの予約はSさんの担当だったので、彼女の携帯電話番号をAには伝えてあったのだった。
そして日が暮れる頃に私たちがゲストハウスに戻ると、Aが歩いて迎えに来てくれた。その前の日は、絵に描いた考古学者のような服装(帽子にベストにジーンズ)だったが、この日は白いワンピースのような、ヌビアの伝統的な装いだった。

前の日から聞いていたことだったが、Aは奥さんと死別し、自分の妹さんとその家族と暮らしているのだという。自分の子どももいるとのことだったが、この日は甥だという男の子しか目にしなかった。Aの妹さんは、「ヌビア人の家庭料理を体験」といったアクティビティで観光客を受け入れることもあるそうで、家の屋上には大人数で食事したりお茶したりできるようなスペースもあった。
私たちはリビングルームのテーブルに通され、妹さん(すでに食べたとのことで食卓には参加しなかった)がキッチンから運んでくれる料理に舌鼓を打った。手作りのパン、豆のスープ、新鮮なサラダ、ふっくらした白身魚…。

Aはワインも開けてくれ、和やかに会話が続いた。ヌビアの文化のこと、学校制度のこと、今はガイドをしているAも、いつかゲストハウスを開きたいという夢があることなど。
雲行きが怪しくなってきたのは、だいぶ食事も進んだ頃である。Aがしんみりと、なんだか少し緊張したような面持ちになったのだ。
「私は数年前に妻に先立たれてから孤独で、ずっと心に穴が開いているような感じがします。ゲストハウスも、一人ではなくて、夢を共有してくれる誰かと一緒に開きたい。…私の心の穴を埋めてくれるのはあなただと、昨日会った瞬間に直感しました。あなたが好きです」
その視線の先にいたのは、私の旅の仲間である日本人女性Hさん。
顔を見合わせる私と、ベルリーナー・Dと、仲間のSさん。顔を赤くして言葉が出てこないHさん。
凍りつくその場の雰囲気。数十秒だったに違いないが、私は気まずい沈黙に耐え切れず、意識が遠のいていくような気がした。
どうにか言葉が戻ってきたHさんは、しどろもどろに、自分は任期付きでドイツに赴任していること、やがて日本に帰らなければいけないこと、気持ちは嬉しいが境遇を考えると現実的ではなく、応えることはできないことを何とかAに伝えた。
Aはそれからも、外国人と結婚したヌビア人の友人の話などを持ち出したが、Hさんの気持ちが変わりそうにないのを見て、しょんぼりと段々口数が少なくなっていった。Dと私は話題を変えようとしたが、もはや気まずい空気は拭えなかったので、美味しい食事ともてなしに感謝して、妹さんにも挨拶し、ゲストハウスに戻ることにしたのだった。
Aはゲストハウスまで歩いて送ってくれた。ちょうどゲストハウスのバルコニーではヌビアの音楽が掛かり何人かが踊り始めたところだったので、Aは私たちと踊りたそうにしていたが、私たちは「明日も朝早起きなので…」とどうにか断って部屋へ引き上げたのだった。
まさかの展開を受けて
ゲストハウスの部屋に戻って少し落ち着いた私たち4人。
勘が鋭いSさんは、「昨日Aがクッキーを買ってきてくれたとき、迷わずHに渡してたでしょ。あれれってちょっと思ったんだよね」と言っていたが、私はまったく異変に気が付いていなかった。Aは、Hさんが結婚していないことは直接確認していなかったようだが、指輪をしていないことなどを観察していたのかもしれない。

純粋なホスピタリティで家に招待してくれたわけではなくて下心があったのか、とDは憤慨していたが、私はあれを下心と呼ぶのはかわいそうだとも思った。会って二日目で告白、というか求婚するのがヌビア文化では一般的なのかはわからないが、50代の男性が気持ちを伝えるには、それなりの覚悟と勇気が必要だったに違いない。
一方で、私が遺憾だった点があるとすれば、Aが持っていた(本人は「インターネットで調べて読んだ」と言っていた)日本人女性のイメージが、半世紀前のステレオタイプと呼んでよく、「日本人女性って、慎ましくて献身的で、家事を完璧にできて、素晴らしいんだね」と言っていたからだ。私はこれを前日にも訂正したのだが、Aはちゃんと聞いていなかったのか、自宅での夕食の席でも繰り返していたのだった。
Hさんは、まさかの展開を受けて、何とも形容しがたい衝撃を受けたようだった。それはそうだと思う。日本からもドイツからも遠く離れた土地で、出会ったばかりのヌビア人に求婚されるなど、誰が考えただろう…。
私たち旅の仲間4人は、複雑な気持ちを抱えたままその日は眠ることになった。ところが、この衝撃はこの日だけでは終わらなかったのである。
ヌビア人キャプテンとの出会い
モヤモヤした気持ちが残った日から一晩が明けた朝。
午前中は、ゲストハウスに手配してもらったドライバー付きの車で、アスワン近郊の観光地(アスワン・ハイ・ダム、未完成のオベリスク、イシス神殿)を巡った。一度ナイル川の中洲にあるゲストハウスに戻って一休みし、それからはボートで、アスワンの中心街とは対岸にあるヌビア村に行くことになっていた。
このボートもゲストハウスに手配をお願いしていたのだが、「ぼくが君たちのキャプテンだよ」と現れたのが、やはりゲストハウスの親戚だという、28歳のヌビア人男性。背が高く細身で、ちりちりのボリュームのある髪をしていて、どこかで見たことがあるような面影…
「ボブ・マーリ―って呼んで」と言われて、ほんとだそっくり!と私たちは爆笑(念のため、ボブ・マーリーはエジプトではなくジャマイカのミュージシャン)。
もちろんこの若者の名前はボブではなく、Mといった。ボートの操縦だけかと思っていたら、ヌビア村の案内もしてくれるという。陽気なリラックスした雰囲気の人で、私たちをジョークで終始笑わせてくれた。
Mがメンテナンスもしているという綺麗なモーターボートに乗り込んで、ゲストハウスを出発したものの、スピードがゆっくりでなかなか目的地に着く気配がない。

日本人女性3人とドイツ人男性1人という私たちの変わった構成についてMに聞かれたので、私とDがパートナーで、HさんとSさんは同僚かつ友達であることを説明した(エジプトにいる間に何度も聞かれたのでもう慣れたものである)。
するとMは、私とDに向かって「君たちお似合いでいいね」と言いつつ、今度はHさんに向かって、「きみ、最初からすごく素敵だと思ってたんだ。ぼくたちもお似合いのカップルになるよ!どう?」と口説き始めたのである。
Hさん、昨日の今日でまさかの二度目の告白。しんみりとしてしまった前日とは違い、Mは陽気で茶目っ気たっぷりだったので、私たち4人は大笑いしてしまった。思わず前日のことをMに話すと、「あぁAか、もちろん知り合いだよ。でもあの人はもう歳だし子持ちだよ。ぼくは若くて独身だから、ぼくにしなよ」という(Aに対してちょっとヒドイ)。
そしてどこからともなく、「きみにだけプレゼント」と石でできたネックレスを取り出し(しかも2つ)、Hさんの首に掛けてあげて、その間にも笑顔で延々と口説いていた。キャプテンがその調子なのでボートは一向に進まない。
「ヌビア村に着いたらお茶もご馳走するよ」というMに、もはや笑うしかなかったHさんは、「私だけじゃなくて全員に奢ってくれたらご馳走になる」と言い、「今日の夜にはカイロ行きの飛行機に乗らないといけないから、はやくヌビア村に行きたいんだけど」とお願いすると、ようやくボートは普通のスピードで進み始めたのだった。

ヌビア村は、水色など鮮やかな色で壁が塗られた建物が並ぶ、可愛らしい場所。混沌としていたカイロと同じ国にあるとは思えない。観光地なので客引きはあるが、カイロほどしつこくはなかった。

まずはMの先導で、彼の行きつけらしいカフェに入ると、まだ小さな男の子が注文を取りに来てくれた。Mは全員分のお茶を注文し、最後には本当に支払ってくれたのだった。
当然のようにHさんの隣を陣取ったMは、お茶を飲みつつ、彼女のことを「Habibi(愛する人)」と呼び、ひたすら明るく口説き続けた。趣味の話になり、Hさんが映画を観に行くことがあると言えば、「ぼくも映画好きだよ、一緒に見たらきっと楽しいよ」と言い、Hさんが任期が終わったら東京に帰らなければと言えば、「ぼくも東京で暮らしてみたい、きみと一緒ならどこでもいいけど」と言う、という具合である…

しかし、Hさんがどうしても靡かないことを感じ取ったらしいMは、カフェを出てヌビア村を案内しながら、少しずつ言葉少なになっていった。また彼のボートに乗り込んでゲストハウスへ戻る時には、行きとは打って変わってMは口数が減り、運転に集中しているようで、行きは1時間近く掛かったのに30分ほどで帰ってきたのだった。
ゲストハウスで私たちを降ろしてくれる時も、Mはにこやかではあったが、それ以上しつこくHさんを口説くこともなかったので、分別がある人でよかったと私もほっとした。
尾を引く経験
まさかの二日続けての求愛を受けたHさん。旅の仲間全員にとってかなり衝撃だったが、幸いにも二日目は明るい人だったので、一日目の気まずい雰囲気の記憶が上書きされ、アスワンを発つ頃には私たちの中ですでに笑い話になっていたのだった。
今考えてもなんともユニークで面白いエピソードだが、ずっと尾を引いて考えさせられる経験でもあった。というのも、エジプト南部から出る機会がなく、閉鎖的とも言える環境で暮らしているヌビア人の彼らと、自由に国を跨いで仕事をし生活している自分たちとの境遇の違いに、どうにもならないもどかしさを感じたからだ。
ガイドのAにしても、歴史や文化財に関する知識が豊富で、ガイドとしての教育は十分に受けた人だとわかるが、エジプトから出たことは一度しかなく、陸路でスーダンへ旅しただけだという。ボートのキャプテンのMは、エジプトから出たいのに出たことがない。
彼らとの共通言語だった英語にしても、私たちは学校教育で学んだり英語圏に留学したりして身に付けたものだが、彼らはアスワンに来る観光客と幼少期から話すことで覚えたといい、自分が外に出て行ったわけではない。
特にMは、ユーモアがあり明るい好青年で、例えば生まれたのがドイツであったなら色々な人生の選択肢があっただろうと思う。ベルリーナー・Dは、日本人女子3人がアスワン中心街のバザールで買い物をしている間、ゲストハウスに残ってMとしばらく色々な話をしていた。
Dは彼に、「ゲストハウスの手伝いだけじゃなくて、ガイドの資格を取ったらいいのに」と勧めたそうだが、Mは「資格を取るための勉強にもお金が掛かるけど、そのお金がないんだ」と答えたという。彼が育った家庭の経済状況は詳しくわからないが、今でも自分の部屋がなく祖母とシェアしていると言っていたから、おそらく裕福な方ではないのだろう。
Mにとっては、外国人女性と結婚してエジプトを出ることが、この場所から離れて新しい生活を始めるための一番の近道、そしておそらくほぼ唯一の道なのかもしれない。
人生とは、生まれた境遇によってなんて不平等なのだろう。もちろん先進国で生まれ育つことが幸せとは限らない。周りとの繋がりが密なヌビア人社会では、私たちとは違う価値観と幸せのかたちがあるはずだし、私たち日本人やドイツ人が上から目線で同情することは正しくないと思う。それでも、日本とヨーロッパで教育を受けて今はドイツで好きな仕事をし、世界中を自由に旅している私には、この「自分で選択できる」人生がいかに恵まれているかが身に染みた。

Dも、自分とほぼ同世代の若者が、外の世界に出たいけれど出られない、という状況にあるのを目の当たりにし、ある種のショックを受けていた。ドイツに帰ってからもWhatsApp(日本でいうLINEのようなアプリ)でMと時々連絡を取り、励ますような言葉を送っていた。
ちなみに、ガイドのAからもまだ時々WhatsAppで連絡がくる。幸いにも、彼が求婚したHさんの番号は教えていなかったので、届くのはSさんの携帯電話だが、まだHさんのことを気に掛けているようだ。そうは言っても、彼がベルリンまで来られることはまずないだろう…。
エジプトではピラミッドの内部に入ったり気球に乗ったり、貴重な経験をたくさんしたが、アスワンでのヌビア人との出会いが、私に一番のカルチャーショックと学びを与えてくれたのだった。
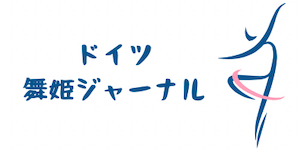



コメント