スコットランドの家庭
前編では、スコットランドのお屋敷に数日泊まってお祝いした友人の結婚式の様子を紹介したが、実はその他の場所でもユニークな経験をした。夫のベルリーナー・Dの同僚かつ友人である男性が、偶然にも同じ地方に一軒家を買って家族と住んでいるというので、結婚式の前後にステイさせてもらったのだ。
この同僚Jは、実はベルギー人。スコットランド在住30年近くで、オランダ企業の英国法人に在宅で勤務している(Dは同じ企業のドイツ法人に在宅勤務)。奥さんのBはスコットランド人で、大学生と高校生の二人の息子がいる。私たちがお邪魔したときは、普段はエディンバラで大学に通っている長男もちょうど夏休みで帰省していた。
私は全員と初対面だったし、DもJの家族とは面識がなかった。このスコットランドの家庭で過ごした数日間が、まさしく「スコットランドでホームステイ体験」と言ってよい、想像以上の濃厚さだったである。
お出迎えの国旗
Jとその家族は、車がないとほぼアクセスできない村に住んでいるという。ベルリンからエディンバラまで飛行機で向かった私たちは、電車で最寄りの大きな町まで移動し、Jに車で迎えに来てもらった。なだらかな丘に羊が群れを成している、見晴らしのよい景色を楽しみながら、30分ほどでJが住んでいる村に到着。
なんと18世紀に造られたという石橋で小川を渡ると、すぐそこにあるのがJの家である。まず私の目が釘付けになったのは、家の側面に掲げられていた日本の国旗!

Jは世界各国の国旗を集めるのが趣味の一つだそうで、「今日はまず日本にしたけど、明日はドイツにしよう」という。以前のアメリカ紀行でも記したが、外で国旗を見掛けることに慣れない私とDは、まさかスコットランドでこんな光景を目にするとは…と笑ってしまった。
二階建ての家は、1912年築という歴史的な建物だ。つまり第一次大戦勃発直前だが、ヨーロッパで資源が枯渇する前なので、この時期の建造物はしっかりしているのだという。中に案内してもらうと、バスルームなどは綺麗にリフォームされているが、基本的には当時の面影がそのまま残されている。9年ほど前にこの家を前の持ち主から購入し、必要のある部分を修復してきたのだという。
中でも面白かったのは、一階のキッチンの横の壁に備え付けられているベル。家の中を紐が張り巡らされていて、その昔は、二階にいる家の主人が紐を引くと、このキッチン横のベルが鳴るので、使用人が二階まで用件を聞きに行ったのだという。ベルの音は大きく、家中に響きわたる。
Jの家族は現在このシステムを逆に利用していて、食事ができるとキッチンからベルを鳴らして、他の家族が一階に集まってくるそうだ。
ジャムが先か、クリームが先か
さて、家の裏には大きな庭が広がっており、私たちが到着したときには、息子二人は芝生の上でホッケーの練習をしていた。庭では、なんとペットだという白い鳩13匹が飼育されている。ケージを開けると外に出てきて家の周りを飛び回るが、逃げることはせずに、疲れると自らケージの中に戻ってくるのが面白かった。

鳩の他に、新鮮な卵を提供してくれるという鶏3匹もいた。もう死んでしまったという以前飼っていた鶏は、ほぼ毎日卵を産んでいたそうだ。でも「不思議なことに、日曜日だけは産まなかったのよ」と奥さんのBが言うので、「日曜日は休息の日だったなんて…きっとクリスチャンだったんだね」と私がコメントすると大笑いになった。
そうこうするうちにBが紅茶を淹れてくれ、スコットランド名物のショートブレッドを食べながら、庭でしばらくお茶タイムとなった。牛乳を入れるのはデフォルトなので、砂糖の有無だけ希望を聞かれる。
イギリスでは「ミルクティーを飲む際に、カップに紅茶を先に注ぐべきか牛乳を先に注ぐべきか」が長年議論されてきて、それぞれの派閥には歴史的な背景や科学的な理由付けがあることなどを教えてもらった。
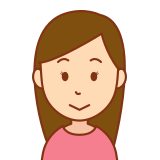
昔の陶器のカップは、いきなり熱い紅茶を注ぐと割れる可能性があったから、ミルクを先に入れてから紅茶を注ぐのが一般的だったの。逆に、先に紅茶を入れても大丈夫な高品質のカップを持っているということは、自慢にもなったと言われているんだって
地域によって「スコーンを横に割って食べる際に、クロテッドクリームを先に塗るべきかジャムを先に塗るべきか」が違うという話もあった。今は亡き女王エリザベス2世は、ジャムが先&その上にクロテッドクリーム派だったそうだ。

ベルギー人から学ぶスコットランド
滞在初日は和やかに終わり、二階のゲストルームで快適に眠った後の翌朝。朝食は9時から、と言われていたので、その時間に一階に下りていくと、Jがベイクドビーンズ、ベーコン、スクランブルエッグ、トーストという典型的な朝食を作ってくれているところだった。

キッチンに立つその姿を見て私とDはびっくり。キルトスカートを着ていたのである。
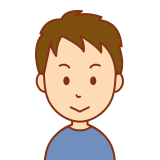
すっかりツアーガイドのような気分になってね。キルト着るの好きなんだ。一式着るのは大変だけど、こんな感じで、上はシャツだけにして、足元はスニーカーを合わせるのもありだよ
という。キルトはスコットランドで結婚式を挙げた20数年前に作ったものだそうだ。母国ベルギーの国旗の色を採用したタータン柄を自ら考案し、タータン登記所に申請し、織工に布を織ってもらい、それをまた仕立屋に持って行って縫ってもらったという、思い入れのこもったキルトだ。
Bは仕事に出掛けていたので、朝食の後は、キルト姿のJとDと三人で近場までハイキングに出掛けた。ベルギー出身だがスコットランドを熟知しているJは、わざわざ私たちのために有休を取り、「普通に観光に来るだけでは見られないだろうスコットランドの魅力を伝えたい」と言ってくれていた。
Jの一家が暮らしている村は、人口2千人弱だが、パン屋や肉屋、食料品店など、日常生活で必要なものが買えるお店は一通り揃っている。
興味深いのは、彼の家がある地域での住所。番地というものがなく、代わりに家の名前が使われているのだ。家、というのは家族のことではなく、建物のこと。それぞれの建物に愛称のような名前がある。日本でいう屋号のようなものだろうか。歴史を感じる習慣である。

良くも悪くも都会から離れたスコットランドのハイランド地方は、車がないとなかなか生活が難しそうな場所ではある。Jの一家は車を二台持っており、息子二人とも運転免許を取るための教習をもうすぐ受けるところだという。
まだ高校生の次男は、彼女が隣町に住んでいるそうで、「バスだと一時間に一本しかないから不便なんだ。早く運転できるようになって、もっと会いに行けるようになりたい」とはにかんでいたのが可愛かった。
一方で、のどかな田舎だと侮ってはいけない。この地方は世界的な有名人も輩出している。例えば、「スターウォーズ」のオビ=ワン・ケノービ役などでおなじみ、俳優のユアン・マクレガー。J曰く、「息子の学校の関係で、ユアンのお父さんと会うことがあるよ」という。そして、「ユアンにはお兄さんがいて、空軍パイロットだったんだけど、『オビトゥー』(オビ1ではなくオビ2)と呼ばれていたんだって」というので、私もDも大笑い。
その他にJが教えてくれたことで言えば、独自の議会システムを持っているなど、いかにスコットランドが独立しているかである。歴史的に別々の王国だったので当然なのだが、スコットランド人とイングランド人は、メンタリティも違えば利害関係も違う。
世界中に衝撃を与えたブレグジット(英国のEU離脱)では、スコットランドと北アイルランドでは残留派が多数だったそうだ。イングランドとウェールズで離脱派が上回ったことに、複雑な思いを抱えた人も多かっただろう。
外来種のリスを…食べる
さて、ベルギー人のJはマルチリンガルで、母語であるフラマン語の他、オランダ語、標準英語、スコットランド英語、ドイツ語も解する。私やDとの会話は標準英語だった。そしてなぜか日本語で「リス」という言葉を知っていた。
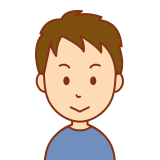
きみが来るっていうから調べたんだよ。リス大好きなんだ
と言い、初日にはダイニングテーブルの横にある窓に案内してくれた。そこは、庭の大きな木の幹に括り付けてあるナッツが入ったエサ箱に、リスが立ち寄ってはナッツを食べる姿を見られるという、「リス観察窓」だったのだ。

このヨーロッパの赤リス(red squirrel、キタリスとも呼ばれる)の可愛さといったら…。小柄な体、綺麗な赤毛、白いおなか、黒いつぶらな瞳、先端がふさふさした耳。
箱に上半身を突っ込んでナッツを取り出すときはアクロバティックな動きをするのに、その後はサッと箱の前にお行儀よく座り、器用に両手でナッツを食べる姿がたまらない。Jが「Aki、リスが来てるよ!」と教えてくれる度に、嬉々として窓に駆け付けたのだった。
私が「ここには赤リスしかいないんだね」と聞くと、Jは首を横に振った。「いや、アメリカ大陸から入ってきた灰色リスが繁殖しすぎて、在来種の赤リスを駆逐したり新しいウイルスを媒介したりして、赤リスの数が大幅に減ってしまったんだ」という。私もこの問題はヨーロッパの他の国でも聞いたことがあった。
アメリカの灰色リスは、赤リスの倍くらいの大きさで、攻撃的な一面がある。昨年アメリカを旅していた時はいたるところで見かけて、最初は「リスだ~可愛い!」と近づいて写真を撮ろうとしていたのだが、「食べ物を持っていると飛び掛かってくることもあるから気を付けて!」と地元の人に注意されたのだった。農作物や自然植生に被害を与えることもあるそうだ。

赤リスを愛するスコットランドでは、外来種の灰色リスは完全に害獣扱い。灰色リスの大量駆除が行われたこともあるという。

Jは、「ぼくもこの近くで灰色リスを見つけたから、駆除したことがあるよ」という。うーん、そうは言っても殺すのもかわいそう…と私が複雑な心境になっていると、Jが続けた言葉に更なる衝撃を受けた。「殺したリスは、もったいないと思ってね、調理して食べたけど、あまり食べる部分がなかったな」。
確かに、リスを食用にしている国があるのも知っているし、ワシントンにあるホワイトハウスのビジターセンターでは、「歴代アメリカ大統領の好物」という展示で「リスのスープ」も挙げられていて、「うわぁ…」と思った記憶がある。しかし、まさかスコットランドの家庭で、リスの調理経験について聞くことになるとは思わなかった。
赤リスを大事にしよう、という意識を別のかたちでも見掛けることがあった。よくある「動物注意」の道路標識は、鹿のイラストがついていることが多いが、スコットランドでは「赤リス注意」というものがあったのだ。赤リスに限定しているところが、裏を返せば、灰色リスであれば轢いていいということなのかな…と思ってしまう。

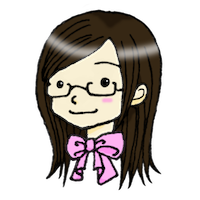
後編の記事では、食べ物など、スコットランドでその他に私たちが感激したものをご紹介します
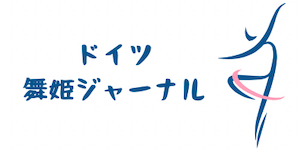


コメント