コーヒーも美味しい
シリーズ中編では、スコットランドのハイランド地方で暮らす友人J一家の元に泊めてもらうことになった話を紹介した。私にとって初めてのスコットランド滞在では、想像と違って驚くことが色々あった。
例えば、スコットランドには美味しいコーヒーを出すカフェがたくさんあることは、どちらかと言えばコーヒー派の私にとって嬉しい驚きだった。イギリス=紅茶、というのがステレオタイプのイメージだが、コーヒー好きのスコットランド人も多いようだ。日本人は緑茶ばかり飲んでいると思われているが、実際にはコーヒーを好む人も多い、ということに近いかもしれない。

後日、「スコーンには紅茶、というのが定番だと思うけど、紅茶じゃなくてコーヒーを頼んでもいいものなの?」とJと奥さんのBに聞くと、「確かに伝統的には紅茶だけど、今はコーヒーを合わせる人も多いよ」とのこと。
ベルギー人のJはコーヒーが大好き。また別の日に車で連れて行ってくれた、郵便局兼キオスク兼カフェのような地元のお店でも、ケーキとカプチーノを注文。

10人も座れないような小さなお店で、私はあまり期待していなかったのだが、店員のお兄さんが丁寧に淹れてくれたコーヒーが驚くほど美味しかった。

長男Fの意外な特技
JとBの長男であるFは、普段は名門エディンバラ大学で物理学の勉強をしている。金髪碧眼、ひょろりと背が高く、文武両道という、絵に描いたような好青年だ。
そんなFには特技があるという。せっかくだから私たちのお客さんに披露してあげて、と両親に言われ、私とDに聞かせてくれたのは、アコーディオン。11歳から習い始め、フランス風の曲から、スコットランドの伝統音楽まで、色々なレパートリーがあるという。毎年ニューヨークで行われている、スコットランドの伝統と文化を祝うイベント「タータンデー・パレード」まで遠征して、楽隊の一員として演奏したこともあるそうだ。
Fにはもう一つの特技があり、こちらは本当に極めるところまで極めていた。それは水切り。
おそらく誰でも一度はやったことがある、水面に向かって回転をかけた石を投げて跳ねさせる遊びだ。しかし「遊び」ではなく立派な競技にもなっていて、水切り世界選手権が毎年スコットランドで開催され、世界中から強者が集うという。
Fはティーンエイジャーにして水切りの技術を極めており、数年前の大会ではなんと優勝。石が跳ねる回数を競う大会もあるそうだが、スコットランドの世界選手権では飛距離で勝敗を決めるそうだ。
ある日の夕食後、みんなで散歩しようという話になり、Jたちの家から20分ほど歩いたところにある川原まで行った。

手ごろな小石がごろごろ落ちているその場所は、Fが子どもの頃から水切りを練習してきた場所だという。その腕前を披露してもらうと、私とDは驚愕。
Fが腰をかがめるようにして、低い位置から回転をかけて投げた石は、すごい速さで小刻みに跳ねながら水面を進んでいく。そして飛距離があまりにも長く、100メートルを優に超えているので、どこで水に沈んだのか私の視力では追うことができなかった。

Fは、小ぶりの石でも、大きめの石でも、うまく力の入れ具合を調節して、遥か彼方まで飛ばしてしまう。「世界選手権、日本人が優勝したこともあるよ。ケイスケ・ハシモトっていう人。投げ方が独特なんだ」といい、腕をぐるぐる大きく回してから投げるというハシモト流も実演してくれた。
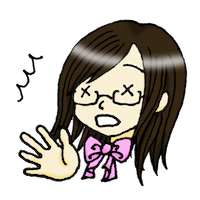
まさかこんな文脈で日本人の名前を聞くとは…!
スコットランドの家庭料理
さて、Jの一家のところに泊まらせてもらったのは、4泊だったが、毎日朝から晩までプログラムを組んでくれていて、あっという間に過ぎていった。車で1時間くらいのところにある大きな街でミュージアム巡りをしたり、DはJと山登りにいったり、私はBとお城に出掛けたりした。
家での食事も、「せっかくだからスコットランドらしいものを」と気を遣ってくれた。最後の夜に作ってくれたのは、伝統料理ハギス(羊の内臓など)を鶏むね肉で包み、ベーコンで巻いて焼いた料理、バルモラルチキン。そこに、レストランでアルバイトもしているという長男Fが作ってくれたウイスキーソースを掛けて食べると、色々な旨味が合わさってなんとも美味しい。

スコットランドといえばやはりウイスキーは欠かせない。スコットランドらしいデザートとしては、クラナカンという、ウイスキー風味のホイップクリーム、蜂蜜、ラズベリー、ウイスキーに浸したオートミールを、何層かになるようにグラスに入れた、パフェのような一品も作ってくれた。
ところで、イギリス英語を学んだことがある人ならご存知だと思うが、イギリスでは夕食を“tea”と呼ぶことがある。その昔、しっかりボリュームのある昼食が一日のメインの食事で、これを“dinner”と呼び、その後に食べる軽い夕食は“tea”と呼ばれたことの名残だそうだ。この地方ではどう使い分けているのだろうと思って、Jのスコットランド人の奥さんであるBに聞いてみると、
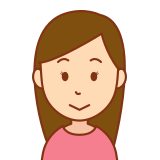
人それぞれで、私も戸惑うことがあるの。夕方のteaに招待してもらって、しっかりした食事が出るというつもりで行ったら、紅茶とビスケットだけ、ということもあったし。相手が迷わないように、私は夕食に招待するときには、dinnerって言ったりsupperって言ったりしているわ
とのこと。“supper”というのは軽めの夕食で、歴史的には夜食を意味することもあったようだ。思い出してみると、私が1年間ステイしていたイングランドのホストファミリーは、夕食をいつもsupperと呼んでいた。
Jの一家にお世話になった数日間で、地元の人の目線でスコットランドの文化やメンタリティに触れることができて、私もDも学びが多かった。滞在最終日は、またJが車でエディンバラまで送ってくれたのだった。
図書館でアフタヌーンティー
最後に、今回のスコットランド滞在での個人的ハイライトをご紹介。それはエディンバラの旧市街でのアフタヌーンティー。滞在最終日、ベルリン行きの夕方の飛行機に乗る前に、Dと二人で出掛けてきた。
イングランド発祥とされるアフタヌーンティー文化だが、もちろんスコットランドでも人気。せっかくだから首都エディンバラでアフタヌーンティーをしたいと調べてみたところ、夢のようなロケーションを発見した。なんと、裁判所の隣にある歴史的建物の図書館がティーハウスとして利用されているのだ。
図書館好きでアフタヌーンティー好きの私にとっては夢のような組み合わせ!数カ月前にオンラインで予約しておいたところ、数日前にはサービス長の男性からメールが届き、アレルギーなどがないか確認してくれた。私はそれに返信する際、「できれば本棚に囲まれた窓際の席がいいです」という希望を書いておいた。
当日になり、予約していた12時半に到着して受付の女性に席まで案内してもらうと、ちゃんと希望していた窓際の席を確保してくれていた。

そこからは夢の時間の始まり。まずアミューズブッシュが出され、セイヴォリーの三段プレート、スウィーツの三段プレート(スコーンは焼き立て)、口直しのシャーベットと続く。

ポットで出されるお茶と、カップで出されるコーヒーは、好きなものを好きな時に頼むことができる。お茶は紅茶・緑茶・ハーブティーなど数十種類から選べて、オリジナルのブレンドも色々とあった。
一緒に行ったベルリーナー・Dは、ドイツ人らしくビールは好きだしコース料理を食べに行くことも好きだが、元々アフタヌーンティーにはあまり関心がなかった。そんなDも斬新な食材の組み合わせに興味津々で、更には頼んだオリジナルのハーブティーがとても気に入り、同じものを2回注文していた。
それが、スコットランド発祥の国民的飲料、アイアンブルーをイメージしたブレンドのハーブティー。アイアンブルーとは、オレンジ色をした炭酸飲料で、スコットランドではコカ・コーラを抑えて一番人気だという。

お茶をサーブしてくれたのはサービス長と思われる、30~40代くらいの上品な男性で、自然な笑顔と柔らかな物腰の、まさにサービスのエキスパートだった。幾つもあるテーブルに常に気を配り、私たちにも適切なタイミングで声を掛けてくれ、お茶を注文すると「素晴らしいチョイスですね」「ぼくも好きなお茶です」とにこやかに頷いてくれる。
Dが気に入ったアイアンブルー風味のハーブティーをお土産に買えないかと聞くと、すぐにキッチンに聞きに行ってくれ、「残念ながら在庫が少なくなっていて販売はできないのですが、レシピを聞いてきたのでお伝えしますね」と、オレンジ・生姜・リンゴ・にんじん・パパイヤ・砂糖…等々と材料を教えてくれた(Dはいつか自分でブレンドできるようにメモを取っていた)。
天井の高い素敵な図書館で、心地よいサービスを受けながら、洗練されたサンドウィッチやスウィーツ、お茶とコーヒーを2時間半ほど堪能。

アフタヌーンティー好きの私は、日本・イギリス・ドイツ・シンガポールなどでアフタヌーンティー巡りをしてきたが、間違いなく上位3位に入る満足度。もしエディンバラに行く機会がある方がいれば、ぜひお勧めしたい。特に「本に囲まれていると落ち着く」という人は間違いなく気に入ってくれると思う。
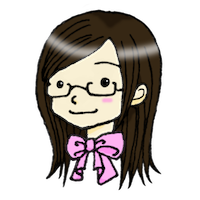
お屋敷での結婚式、ホームステイ体験、図書館でのアフタヌーンティーと、内容盛りだくさんのスコットランド滞在でした
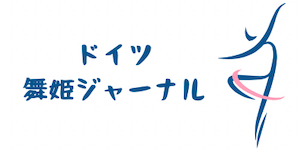



コメント